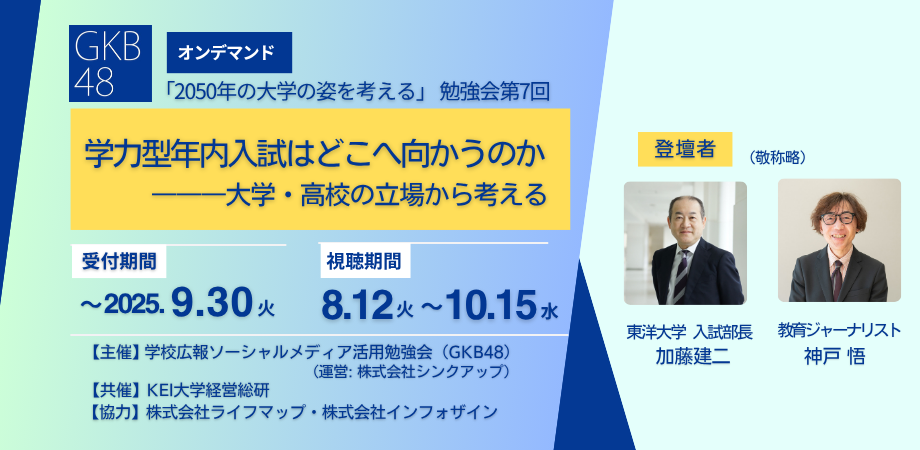2025年7月30日(水)、GKB48は大学の入試広報担当者と高校進路指導教員を対象に、年内入試の今後をテーマにしたセミナーを跡見学園女子大学(東京都・文京区)を会場に開催しました。近年、大学入試において一般選抜から年内入試へのシフトが加速する中、受験生の基礎学力をどう担保するかは、大学・高校双方にとって喫緊の課題です。また同時に大学にとっては少子化の局面において入学者確保を念頭に入試戦略を考える必要があります。今回は東洋大学 入試部長の加藤建二氏と、教育ジャーナリストの神戸悟氏が、それぞれの視点から現状と課題、今後の展望を語りました。(主催:GKB48(運営:株式会社シンクアップ)、共催:KEI大学経営総研、協力:株式会社ライフマップ、株式会社インフォザイン)
加藤氏による講演「年内入試の学力試験を考える」では、東洋大学が昨年度導入した「年内入試における基礎学力試験」の経緯や狙いが紹介されました。一般選抜と年内入試で入学してくる学生の基礎学力差、文科省とのやり取り、そして導入による成果や課題が、具体的な数字や制度設計の工夫とともに示されました。また、多科目型入試や英語外部試験利用、数学必須化など、長期的視点で進めてきた入試改革の背景にも触れられました。加藤氏は「どの入試形態でも最低限の教科・科目の基礎学力は測るべき」と強調し、大学ごとの現状認識の重要性を訴えました。

神戸氏による講演「学力型年内入試と入試制度の行方──2026年度入試への影響」では、外部から見た制度改正の経緯や各大学の対応事例が分析されました。文科省による「大学入学者選抜実施要項」の巧妙な表現(ルール)変更、学力試験実施の条件、各大学が取り入れた小論文や面接の位置づけなど、報道だけでは見えにくい動きが明らかに。さらに、国公立大学の推薦枠拡大や、共通テストの動向が今後の受験行動に与える影響についても言及があり、「年内入試対策としての面接や志望理由書作成は特別な指導ではなく、日常の学び(グループワーク、発表)の中で鍛えるべき」という提案が印象的でした。
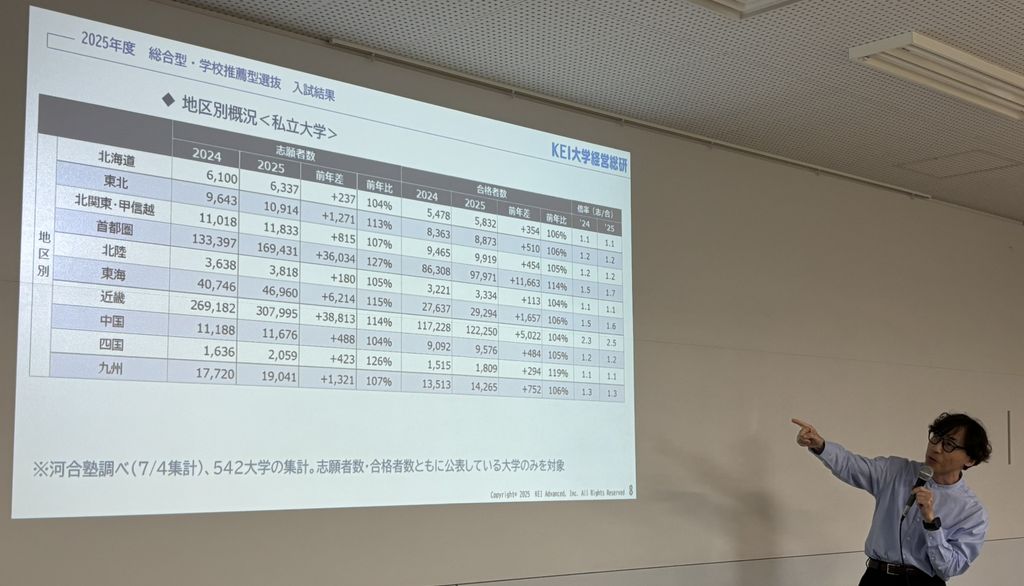
後半のグループディスカッションでは、高校と大学の参加者が混ざり、年内入試の課題や高校生の進路選択、受験指導など、双方への現場の状況を積極的に情報交換がされる様子が見られました。(参加者50名)。
参加者からは下記のような感想がありました。
・今回も、大学の有益な最新入試動向を同僚に共有できる(高校)
・ディスカッションを通じて大学の募集担当者の方々に、高等学校の進路指導や高校生、保護者が求めていることをお伝えすべきことを痛感した(高校)
・入試を軸に、いろいろな考えや各大学の現状を肌感覚で知ることが出来て、とても有意義。今後の大学や高校の在り方を考えるうえでも重要な時間だった(大学)
・東洋大学は常に確認する対象ではあるが、今回の講演では、全体を網羅したご報告及び大規模大学であってもさらに目指す姿をもち、実現している様子が理解できた。神戸氏のご報告も国公立は普段チェックがおろそかになりがちなのでありがたい内容だった(大学)
・大変学びの多い、楽しい勉強会になった。講演の人選・内容が素晴らしかったのはもとより、グループディスカッションでも参加された皆さまが積極的に意見交換してくださって大変有意義な意見交換ができました。

今回の内容は、制度改正の背景や各大学の対応、今後の大学入試戦略の検討や、高校生の受験指導を検討するうえで必聴です。データや資料だけからでは読み解きにくい、背景や意図に関する分析や解説が非常に貴重でした。講演部分のオンデマンド受講も可能ですので、お申込いただければ幸いです。
(申込締切:2025年9月30日)